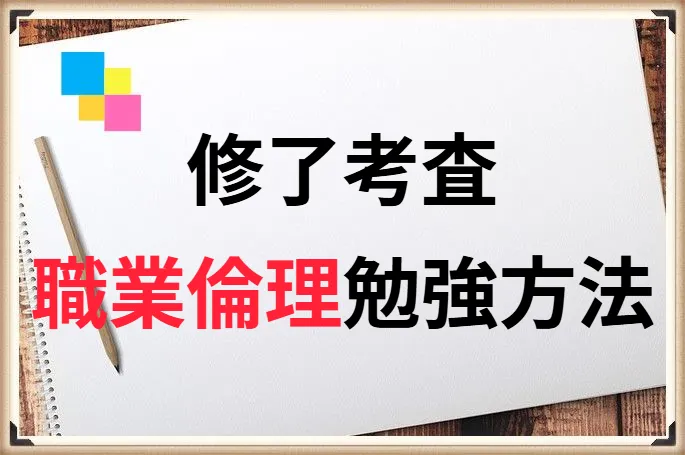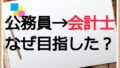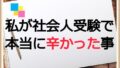この記事は以下のような方におススメです。
・職業倫理の具体的な勉強方法が知りたい方

こんにちは!とむやむくんです。
修了考査と言えばご存じの通り、公認会計士登録するための最後の砦、最後の試験。
修了考査本番では最後の科目になる、公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理、いわゆる「職業倫理」です。
配点は100点と他科目の1/3なのですが、きちんとした対策をしないと…痛い目に合います。
①全て暗記することは到底不可能
②配点は低いが足切りが多い科目
③過去問、答練箇所を中心にした対策が最重要
これから紹介する勉強方法は私が実際に試してこれは効果があったな、と思うものをまとめたものです。
あくまでも一つの勉強法として参考になれば幸いです。
(一応今回は修了考査まである程度時間がある方向けに書いています)
☆この記事の信頼性について
筆者は実際に修了考査を受験、一発合格しており、合格者として職業倫理の勉強法を発信しています。
今の法人から一刻も早く『脱出』したい方へ
BIG4の雰囲気にもううんざり…
膨大なタスク・残業がキツイ…
監査なんてそもそも好きじゃない…
→何も今の職場に執着する必要は"全く"ありません
・未経験から他業種への好待遇転職
・もはや完全に残業しない、週3勤務
⇒こんなのは『簡単に』達成可能です。
ご存じかとは思いますが、転職市場での会計士(合格者)の評価は半端じゃないです
ただ、会計士の価値をよくわかっている専門のエージェントでないと、大失敗することがあります。
私は業界に精通しており、業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。
もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓
職業倫理の勉強方法:基本方針
修了考査の職業倫理における出題範囲をご存じでしょうか?
修了考査の受験案内には以下の通り記載されています。
公認会計士が行う業務で必要とされる職業倫理等の規制及び法令による公認会計士に対する
規制を修得しているかどうかの確認を行うことを目的に出題します。
(出題に関する基準・出題項目等)
公認会計士法、同施行令、同施行規則
日本公認会計士協会会則、倫理規則
金融商品取引法による監査人に関する規制
会社法による監査人に関する規制 等
日本公認会計士協会「修了考査について」より抜粋
うーん他の科目と比べれば少ない…?
と思われたかもしれませんが、修了考査の中では最も配点の低い100点。
会計実務・税務実務・監査実務は300点、経営実務は200点ですから、かなり低い点数になっています。
予備校のテキストを見ても薄いことが分かると思います。
ただ、その分出題問題数も少ない傾向にあり、しっかり対策しないと足切り(40%以下)を平気で取る科目でもあります。
一時よりは問題数が増加したようで、そのリスクも減ってきてはいますが
それでも範囲狭いからテキトウでいいか…なんてやってると普通に足切りです。
(私が本番を受けた時もやたら難しくて普通に終わった…と思いました)
なので職業倫理の基本方針としては
時間をめちゃくちゃかける科目ではないけど、覚えるところはしっかり覚える
となります。
職業倫理の具体的勉強法
さて、範囲が狭いからと言って手を抜くのはNGというのはご理解いただいたと思いますので、
具体的な勉強法について紹介していきます。
・答練対策
・予備校の利用
それぞれについて解説していきます。
(なお、他科目とも重複する箇所が多いことはご了承ください)
過去問対策
修了考査のどの科目にも言えることですが、
過去問対策と答練対策は必ず必要です。
会計士試験と違い、入念な試験対策に割く時間がない中、
大半の方が対策してくるのがやはり過去問と答練だからです。
そんな過去問対策ですが、私の場合は
予備校で配布された過去3年間分(+1年分)
については、全てテキストの該当箇所にマークをし、対策をしました。
+1年分、とあるのは通常予備校で配られるのは3年分なのですが(TACはそうでした)
私の場合1年間都合で受験することができなかったので、その時にもらった過去問が余計に1年分あったためです。
ところで私が受験した2024年の修了考査では、
テキストに載っている…?載っていない…?
いや聞いたこともない…
という問題結構出ました(周りの方もそんなこと言ってました)
なので必ずしもテキストに全てチェックは付けられないかもしれませんが、
その場合はその箇所だけ分かるようにして過去問を随時参照するようにしましょう。
答練対策
答練についても先ほど書いたように対策が超重要です。
やり方は過去問と同じですが、
答練出題箇所をテキストにマークし、対策をしました。
職業倫理の答練はどこの予備校もそうかと思いますが、1回位しか答練がないので
その範囲は少なくても全てカバーするようにしましょう。
予備校の利用
予備校については私は利用すべきだと考えています。
大半の方が利用していますし、何と言ってもやはり費用対効果は高いと思います。
補習所のテキストから対策…となると、やはりかなり厳しかったです(私は)
監査法人勤務の方の多くは、予備校代も補填してくれる場合があるでしょうから、通わない手はありません。
(どこかで記事も書こうかとは思っていますが、体感ではCPAとTACが多く、CPAが一番多い印象です。)
さて、職業倫理における予備校の利用についてですが(私はTACでした)
全てきちんと聴講し、できる限り補足のメモも取りました。
TACの職業倫理のテキストは非常にわかりやすく、重要度表記や過去問も多く掲載されています。
ただ、講義の中で講師の方が重要と言っている箇所や、補足で説明を加えている箇所は加えてテキストに記載することで
理解度が全然違ってきます。
あー、ここが改正されたんだ…
あーここは重要だけど去年出たけど重要度は下がるんだ…
あんまり出てないけど今年は重要なトピックなんだ…
こんな感じですね。
まあ何よりも印字された文字面を追っているよりも、
自分で書き加えたテキストの方がやる気も理解度も全然違います。
職業倫理に関しては、ここは絶対暗記する!という箇所が何か所かあります、
例えば「公認会計士の使命」「公認会計士の職責」「基本原則」「阻害要因」みたいな箇所ですね。
こういったところはガッツリ暗記しておかないと出題されて落とした時かなり痛いです。
面倒かもしれませんが暗記するようにしておきましょう(講義でも言われると思います)
職業倫理の時期別勉強方法
具体的な勉強方法は記載した通りですが、
職業倫理の勉強法について、初期・直前期に分けて解説します。
職業倫理初期の勉強方法
初期の勉強法としては
・答練出題箇所にチェック
・A論点、B論点を中心に読み込み
となります。
(答練については1年前のものを私は入手していましたので、勉強初期からチェックはできていました)
C論点に関しては、答練や過去問箇所は読みましたがほぼスルーしました。
最初期に関しては読み込むためのテキストを作り込む、というのを念頭に勉強をしていました。
ここでどれだけ充実した(書き込みをした)テキストを作ることができるかが重要です。
そしてテキストが完成したらそれをできるだけ短期間で読みまくる、私は1週間で1周を目標にしていました。
職業倫理直前期の勉強方法
初期と同じような勉強法でしたが、今回の答練の箇所はさらに注意力を上げて読み込みを行いました。
また、テキストに載っていないような問題も答練では出題されますから、
そういった箇所は答練に戻って読み込むようにしていました。
その時、どこが答練にしか載っていない問題かをきちんと把握するため、答練にチェックするようにしていました
(毎回探す手間を省くため)
職業倫理に関しては、先ほど少し書いたような必須の暗記箇所については
試験の直前まで呪文のように繰り返し唱えるくらい気合いを入れて覚えていました。
(なんだかんだ何問か毎回出題される印象です)
おまけ:職業倫理ってどれ位勉強したの?
配点も少ないですし、範囲も少ない職業倫理。
勉強時間をどうとっていくかなかなか悩むところかとは思います。
私は監査実務の勉強範囲の一部としてとらえて、監査実務と同じ頻度で勉強をしていました。
もしかしたらやりすぎ、なのかもしれませんが
色々調べると足切り怖い、職業倫理のせいで落ちた、なんて話をよく見たので怖くなった、というところはあります。
正直私が受験した回では、勉強した意味あった…?と思う所も多くありました。
ですが、それは受験生全員が思っていたことで
みんなが取れる問題を確実に取っていけば大丈夫です。
結局それが頻出の暗記箇所や答練の箇所・過去問の箇所なので、
対策として特に奇をてらう必要はありません。
さいごに
職業倫理については、テキスト薄いくせによく手に取っていたなあ…という印象です。
本番の手応えは結構最悪でしたが、それなりの成績は取れたので
まあそこは絶対評価といえども何らかの配慮をされた上での、という話を信じるしかないでしょう。
(この点についてはいずれ書いていこうと思います)
受験される方は過去問・答練・テキストと当たり前の対策をしておけば大丈夫です。
暗記大変ですけど、我慢してやり切りましょう!