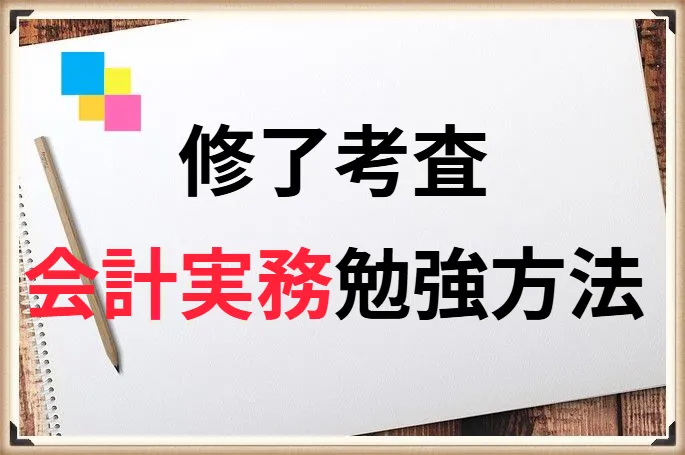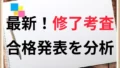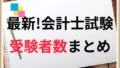この記事は以下のような方におススメです。
・会計実務の具体的な勉強方法が知りたい方

こんにちは!とむやむくんです。
修了考査と言えばご存じの通り、公認会計士登録するための最後の砦、最後の試験。
その最も重要な科目ともいえるのが、会計に関する理論及び実務、いわゆる「会計実務」です。
範囲が膨大なこともあり、勉強方法に一番苦労する科目とも言えます。
①簿記(計算)の範囲を全て網羅することはできない
②理論の範囲も全て網羅はとてもできない
③過去問、答練箇所を中心にした対策が最重要
これから紹介する勉強方法は私が実際に試してこれは効果があったな、と思うものをまとめたものです。
あくまでも一つの勉強法として参考になれば幸いです。
(一応今回は修了考査まである程度時間がある方向けに書いています)
☆この記事の信頼性について
筆者は実際に修了考査を受験、一発合格しており、合格者として会計実務の勉強法を発信しています。
今の法人から一刻も早く『脱出』したい方へ
BIG4の雰囲気にもううんざり…
膨大なタスク・残業がキツイ…
監査なんてそもそも好きじゃない…
→何も今の職場に執着する必要は"全く"ありません
・未経験から他業種への好待遇転職
・もはや完全に残業しない、週3勤務
⇒こんなのは『簡単に』達成可能です。
ご存じかとは思いますが、転職市場での会計士(合格者)の評価は半端じゃないです
ただ、会計士の価値をよくわかっている専門のエージェントでないと、大失敗することがあります。
私は業界に精通しており、業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。
もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓
会計実務の勉強方法:基本方針
修了考査の会計実務における出題範囲をご存じでしょうか?
修了考査の受験案内には以下の通り記載されています。
公認会計士が行う実務としての会計業務で必要とされる実務に関する専門的応用能力を修得しているかどうかの確認を行うことを目的とし、我が国における会計に関する理論及び実務全般について出題します。
〇出題に関する基準・出題項目等〇
・企業会計審議会が設定した企業会計に関する原則、基準、取扱い
・企業会計基準委員会が設定した会計基準、適用指針、実務対応報告
・金融商品取引法に基づく会計に関する関連法規、ガイドライン
・会社法に基づく会計に関する関連法規
・日本公認会計士協会会計制度委員会報告
・国際財務報告基準
日本公認会計士協会「修了考査について」より抜粋
まあ、つまり何が言いたいかというと
・公認会計士試験の短答式の財務諸表論範囲
・公認会計士試験の論文式の財務諸表論範囲
・補習所における考査の範囲
これ、全てが試験範囲です
(なんならプラスアルファされてるのでは…、こんなの考査でやったっけ?というのもたくさんありました)
そう、これらの範囲を全て対策するなんて、到底無理なわけです。
まして大半の方は働きながらの受験になるわけですから、時間は有限。
元々会計士試験時代から大得意で(なおかつその記憶が今も残っているなら)、というなら問題ないかもしれませんが
まず全ての範囲を徹底的に対策することはコストパフォーマンスが悪すぎる、ということは念頭に置いておきましょう。
会計実務の勉強法:計算理論共通
さて、全ての範囲を徹底的に潰すのが難しいのはご理解いただいたと思いますので、
具体的な勉強法について紹介していきます。
まずは計算・理論に共通する勉強方法として
・答練対策
・予備校の利用
それぞれについて解説していきます。
過去問対策
修了考査のどの科目にも言えることですが、
過去問対策と答練対策は必ず必要です。
会計士試験と違い、入念な試験対策に割く時間がない中、
大半の方が対策してくるのがやはり過去問と答練だからです。
そんな過去問対策ですが、私の場合は
まず『理論』については
予備校で配布された過去3年間分(+1年分)
については、全てテキストの該当箇所にマークをし、対策をしました。
+1年分、とあるのは通常予備校で配られるのは3年分なのですが(TACはそうでした)
私の場合1年間都合で受験することができなかったので、その時にもらった過去問が余計に1年分あったためです。
次に『計算』については
私は過去問を徹底的に抑えることはしませんでした。
同じ問題が出題されることはまずないでしょうし、回によっても難易度が全然違うからです。
ただ、出題傾向、この範囲はよく出るな、というのはもちろんあるので、
よく出題される分野等、解かないまでも出題方法については見るようにしていました
答練対策
答練についても先ほど書いたように対策が超重要です。
『理論』については過去問と同じですが、
答練出題箇所をテキストにマークし、対策をしました。
私は答練対策がかなり肝になってくるかな、と思う所がありましたらから
1年前の答練も入手し、対策を行っていました(TAC、CPA共)
ここまでする必要はないかもしれませんが、私は不安だったのでやってました(絶対受かりたかったので)
『計算』については
受験年の答練はもちろん受けましたが、何度も解き直すようなことは私はしていませんでした。
↓
ここまでの難易度で出題されることはないだろう
↓
出されたとしても、結局合否を分けるのは基礎的な部分だろう
↓
重要なのは答練出題範囲の基礎だろう
ということで、出題範囲と傾向のみを分析するにとどめて、
その範囲の基礎的な部分は徹底的に抑えるようにしていました。
予備校の利用
予備校については私は利用すべきだと考えています。
大半の方が利用していますし、何と言ってもやはり費用対効果は高いと思います。
補習所のテキストから対策…となると、やはりかなり厳しかったです(私は)
監査法人勤務の方の多くは、予備校代も補填してくれる場合があるでしょうから、通わない手はありません。
(どこかで記事も書こうかとは思っていますが、体感ではCPAとTACが多く、CPAが一番多い印象です。)
さて、会計実務における予備校の利用についてですが(私はTACでした)
私は講義は聞いていません(ごめんなさい)
1・2回分は聞いていたのですが、正直私にはあまり合わず…(TACさんごめんなさい)
テキスト自分で読めばいいのでは?と思ってしまったので
講義は聞かず、それ以外のテキスト、問題集、答練等を大いに利用していました。
会計実務の勉強法:計算
それでは次に会計実務の計算の範囲における勉強方法について書いていきます。
計算は範囲が多く時間もかかるので、初期の勉強が結構重要だと私は考えています。
初期
私は簿記が得意ではありませんでした。
なので、徹底的に基礎を鍛え直そう、と考え配布された計算テキストをとりあえず一周回しました。
まあできないできない、ストックオプションとかその辺りの簡単な問題も間違えてました。
論文から数年たつとこんなに忘れるんだ…と痛感しました。
↓
間違えたところをテキストにメモ
↓
2周位したらあとは2ヶ月に1回解き直し
のようなスタイルで定期的に解き直すことで忘れないようにしていました。
直前期
11月位からは頻出箇所を徹底的に潰すことに専念していました。
先程も書いたように過去問、答練の解き直しはほぼしていません。
ただ、答練の出題箇所については注意していましたから、答練に出てきた範囲で修了考査テキストにないものは会計士試験時代のテキストでフォローしたりしていました。
CPAの計算テキストは見ていませんが、TACの計算テキストは修了考査の頻出論点のみが載っていたため、全論点が掲載されているわけではなかったためです。
捨てた範囲
捨てる、というのはあまりよくないとは思っていますが、
・答練で出題されていない箇所
加えて、過去の実績を見てもあまり出てないし、
テキストにはあるけど時間はかかりそう…という以下の論点は正直あまりやっていませんでした
・結合、分離の複雑な論点
・キャッシュフロー計算書
・連結キャッシュフロー計算書
もちろんここは個人の判断になりますので、あくまで参考にお願いします。
会計実務の勉強法:理論
理論も本当に範囲が膨大で…
どこから手を付けたらいいのかわからなくなりましたが、
なんとか私なりの勉強法を見つけて対策していましたので紹介します。
初期
私はTACの修了考査がとても合っていて、
予備校に悩んでいる方がいれば安心してお勧めするのですが
会計実務の理論については少し合わなくてですね…(講師の方は今は変わっているようですが)
講義は合わないし、テキストもあまりわかりやすいとは言えないし…
ということでかなり悩みました。
結局、先ほども少し書いたように
過去問(3年分+1年分)と答練の出題箇所をテキストの該当箇所にマークし、徹底的に暗記する、という方法に落ち着きました。
ついでに言うと不安だったのでCPAの会計実務理論のテキストも取り寄せてA,B論点を読み込みもしました。
(会計実務理論のテキストに関してはCPAの方が断然わかりやすかったです)
さて、話は少し脱線しましたが、
テキストに答練過去問の出題箇所を書き込んだら、1週間で1周するように読み込みを行っていました。
期間が空くと覚えられない、忘れる、ということは会計士試験時代に散々体験していましたから、その対策です。
直前期
理論については直前期でも基本的な勉強方針は変わりませんでした。
ただ、答練の箇所はさらに注意力を上げて読み込みを行い、抜けが無いようにしていました。
さいごに
つらつらと書いてきましたが、いかがだったでしょうか。
私は個人的には会計実務の勉強が一番大変でしたし、やりたくありませんでした。
本番の手応えとしてはそうですね…
「いや、勉強した意味…」
と思う所は多くありましたが、それは恐らくどの予備校の方も一緒だと思います。
ただ重要なのは受験生が取れる問題を確実に取りきることですから、
その中でも落ち着いて取れる問題は取る、というスタンスは変わりません。
きちんと対策すれば70%以上は通る試験にはなっていますから(現状は)
これを読んでいるような勉強熱心な方はまず大丈夫だと思います。
大変だとは思いますが、会計登録まであと少し!頑張りましょう!