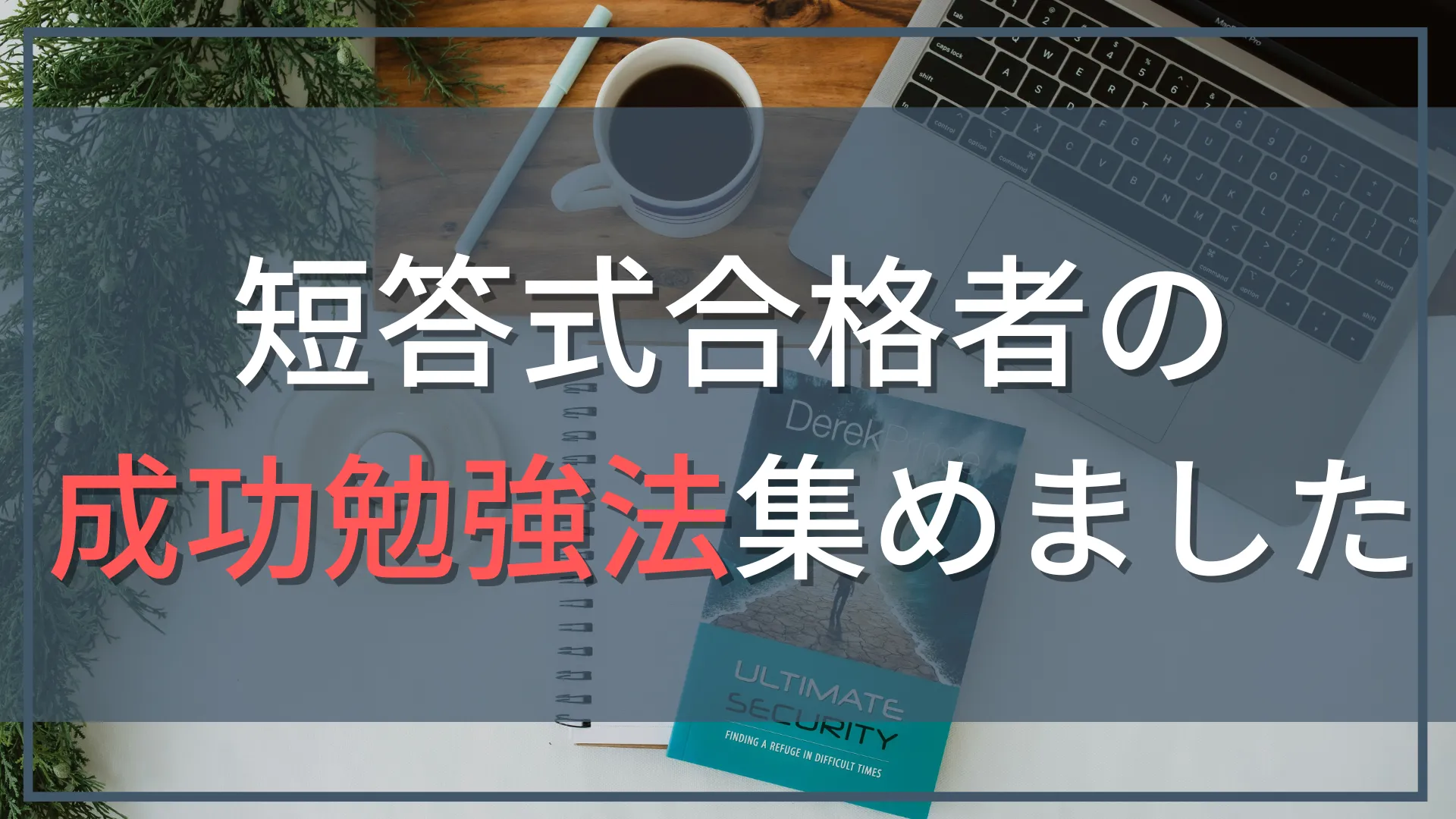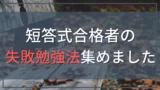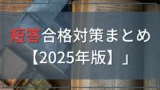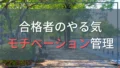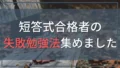・公認会計士試験短答式の合格者の勉強法
・公認会計士試験短答式合格者の生の声

短答式合格者の成功した勉強法だけ集めました。
・30代で働きながら公認会計士試験合格
・修了考査合格、公認会計士登録済
・SNSフォロワー1万人超アカウントで情報発信中
・自ら合格体験記、アンケートを収集し情報を分析
こんにちは!とむやむくんです。
SNS等でもいろいろな勉強法があふれていて、
実際どの勉強法が自分に合っているのか?効果がある勉強法はどれなのか。
判断するのはなかなか難しいですよね。
今回は私自ら収集した合格体験記の、短答式合格者10名の「これは良かった勉強法」だけを集計・分析してまとめました。
ここにあるノウハウはすべて短答合格者の実践から来た“実用”です。
【ストップ!!】監査法人就職のウラ技
簿記を勉強している。前職がある。
実は、これだけで十分就職可能です。
・試験休暇なんと3ヶ月
・年収500万以上
⇒これが『今すぐ』実現できます。
合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。
ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。
情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。
私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。
もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)
まず押さえるべき!合格者に共通する3つのマインドセット
具体的なテクニックに入る前に、多くの合格者に共通しているマインドセットを3つご紹介します。
このマインドセットを持つことが、学習効果を最大化する第一歩です。
完璧主義はNG!知識を重ねる「ミルフィーユ学習法」
合格者は、一度で全てを完璧に理解しようとは考えていません。
(本当にたまに、画面記憶できる方とかいますが、それは例外として…)
薄い知識を何度も何度も繰り返し塗り重ね、層のように知識を固めていくイメージです。
【合格者の声】
1つの内容に時間をかけない。完璧に理解しようとしない。薄く広く何度も繰り返し回転しミルフィーユのイメージで少しずつ定着させていく。
これ私も本当に重要だと思っていて、
特に財務会計論理論とか、何度読んでも読んでも理解できない(組織再編とかその辺り難しいですよね…)
1ページ読むのに1時間もかかっていた…なんてことはよくあります。
わからない論点にぶつかっても、悩みすぎずに次に進みましょう。
2周目、3周目と繰り返すうちに、完全に理解できないまでも、試験で正答できるくらいには必ずなります。
「わかる」より「できる」へ!高速反復こそが正義
先ほどのミルフィーユ学習法と似ていますが、ある程度「理解」に時間をかけることは大切ですが、
それ以上に合格者が重視していたのが「思い出すスピードを上げること」、つまり高速で反復することです。
【合格者の声】
理解に時間使うのも大事だが、そこにだけこだわるのではなく、再度確認できるまでを早くするほうが大事だと感じた。
【合格者の声】
間違えことを毎日正解するまで反復する方法。計算でも使っていました。
後ほどもでてきますが、人間の記憶は復習するタイミングで記憶の定着率は全然違ってきます。
何とかして理解してやる!とそこだけに時間を使うよりも
先ほどのミルフィーユ学習法のように何回も学習する+高速回転で短期間で何度も目に入れるようにする
これが超重要です。
特に時間のない方にはオススメです。
(社会人受験生だった私にとってもこの勉強方法は生命線でした)
直前期は爆発的に伸びる!「土台作り」を信じる
テキストに書き込みをしたり、間違えノートを作ってみたり、
勉強初期にはやることがたくさんあります。
ですがここでどれだけ教材を作りこめたかどうかが合否を分けます。
と、いうのも
みなさん学校の定期試験を想像していただければわかるかと思うのですが
試験前日とかめちゃくちゃ暗記はかどりませんでしたか?
それと同じで、直前期は危機感やプレッシャーからものすごく勉強効率が上がります。
【合格者の声】
初学者は直前1か月で一気に伸びる。目先の答練の得点や判定に惑わされず「直前期に高速回転する」土台作りをいかにできるか、が勝負だと思う。
面倒かもしれませんが丁寧に教材を作る。
そしてそれを直前期に高速回転させる。
これが超重要です。
【科目共通】学習効率を最大化する神テクニック7選
ここからは、計算・理論問わず全ての科目で使える、
合格者の方々が、学習効率を高めるために行っていた具体的なテクニックをご紹介します。
スキマ時間を制する者は短答を制す
合格者は、通勤・移動中、食事中など、あらゆるスキマ時間を学習に充てています。
たかが5分でしょ…と思われるかもしれませんが
この数分の積み重ねが、本当に効いてきます。
なんか短い時間のほうが勉強がはかどることさえ、あるんですよね。
【合格者の声】
隙間時間で理論のweb問題集を解きまくる (お風呂や移動中、トイレ、食事中、布団の中など)。何周解いたかわからないぐらい何回も解きました。
スマホやタブレットでアクセスできるWeb問題集やWebテキストを利用できる予備校であれば
それらを駆使すればスキマ時間の学習の強力なツールになります。
自分だけの「ミスノート」を作成する
間違えた箇所、最初は悔しい思いでいっぱいになりますが、
それは本試験でも間違える可能性が大いに高い場所です。
ノートを作るかどうかは別として、
短時間でぱっと見返せるように、ミスをした箇所をまとめている合格者の方は多かったです。
これ、本当に自分だけの最強の復習ツールになります。
【合格者の声】
コンサマに「間違えた論点をメモする」方法が効果的だった。自分だけの弱点集を作ることで試験直前に効率よく復習できた。
どう記録するかは人それぞれですが、
ノート、テキスト・問題集への書き込み、付箋等、自分に合った方法を選んでください。
インプットとアウトプットを1セットで行う
テキストを「読む」だけで終わらせていないでしょうか。
(私はどちらかといえば終わっていました…そのせいで点が伸びなかったのかもしれません)
合格者は読んだ直後に「自分の言葉で説明できるか」を確認する作業を取り入れています。
こうすることで記憶への定着率が劇的に向上します。
【合格者の声】
理論科目で、テキスト等で内容を確認した後に、テキストを見ずに書いてあった内容(重要部分)を言えるか。これをすることで理解が進むとともに暗記した成果となる。
自分の言葉で、というところが大事です。
文言をそのまま暗記してもいいのですが、これは記憶に残りにくいです。
また、テキストの「音読」も、内容を頭の中で整理しながら記憶に定着させる効果的な方法です。
答練の成績に一喜一憂しない
今回の答練、全然できなかったなあ…
気持ちはとても分かりますが、答練の結果に一喜一憂しなくても大丈夫です。
答練の真の価値は、
・自分の弱点を発見すること
・現状の自分のランキングを知ること
にあります。
【合格者の声】
答練は勉強した範囲が問題として出てきて解けるだけ定着しているか確認するために使う
答練をメインに回転教材にしている合格者の方は私の収集した情報の限りではいませんでした。
重要な論点はどこなのか(半数以上が得点している論点を落としていないか)
極端にミスの多い論点はないか(理論だけ壊滅していたりしないか)
合格者全体から見て自分の順位はどうか(簡単な問題を落としていなければ合格圏内に入ってはいないか)
この辺りを重点的に確認、復習しましょう。
デジタルツール(iPad・AI)を使いこなす
現代の受験勉強では、デジタルツールをいかに活用するかも重要です。
【合格者の声】
iPadのwebテキストでテキストの確認作業をしながら手元の問題を復習するのはテキストが散乱せず効率よく勉強できた
【合格者の声】
分からないことは一旦AI(私はchat GPTを使いました)に聞いてみた。どこに書いてあるとかの当たりをつけるのにも便利だった。
Webテキストで学習場所を選ばない環境を整えたり、
AIを壁打ち相手にすることで、
学習の効率と深さを格段に向上させることができます。
(AIは間違った情報、古い情報のこともあるので、しっかり根拠は確認する必要はあります)
忘却曲線を利用した計画的な復習
ご認識の通り、人間の脳は忘れるようにできています。
ただ実はこの、忘れる、というのはある特性があり、
ベストなタイミングで復習することで記憶の定着率をグッと上げることができます。
【合格者の声】
講義でやったところは授業の日から、次の日、3日後、1週間後、1ヶ月後のペースでテキストを読み返していた。エビングハウスの忘却線を参考にしていた。
エビングハウスの忘却線というのは、
学習時間からどれ位経ったらどれ位忘れていくのか、というのを表したもので、
復習のタイミングを知るのに便利です
(学習直後の忘却率が高いため早期の復習が重要、のようです、詳細はぜひ調べてみて下さい)
このサイクルを意識するだけで、記憶の定着率が断然変わります。
自分に合った復習の頻度を見つけましょう。
とにかく寝る!
睡眠時間を削って勉強する、という意気込みは素晴らしいですが
合格体験記を読んでいても、みなさん睡眠時間はしっかり確保している方が多いです(8時間とか)
実際、多くの合格者が「睡眠の重要性」を挙げています。
ウトウトしながら勉強する1時間より、しっかり寝てからの30分の方が何倍も効率的に感じるはずです。
【合格者の声】
とにかく寝る(ウトウトしている時間は無駄)
私も実際睡眠時間を削って勉強していましたが、
極端かもしれませんが、睡眠不足の10時間より、たっぷり寝た後の4時間の方が効率的に勉強できていたと思います。
【計算科目】得点力を爆上げする攻略法
計算科目は一朝一夕で点数を上げることが難しい上、
漠然と問題集を回していても点数が上がらないやっかいな科目です。
ここでは合格者が実践していた、得点力を安定させるためのテクニックをご紹介します。
応用問題より「テキストの例題」を完璧にする
点数が上がらない、これはきっと私の演習が足りていないんだ…
まだまだ難しい問題を解けるようにならないと受からない…
とこんな感じで
焦ってめちゃくちゃ難解な論点や、難しい問題集に手を出していませんでしょうか。
本当に計算科目については何回でも言いたいのですが、
合格への一番の近道は、テキストに載っている基本的な「例題」を完璧に解けるようにすることです。
【合格者の声】
下手にコントレに手を出さなかったこと。例題で十分だった。
【合格者の声】
計算は直前までテキストの例題も回転する。直前だからといって応用問題ばかりに気を取られないようにする。
例題レベルの問題を落とさなければ試験では間違いなく合格できます。
合格できないのは基礎ができていないことケースが大半です。
「目解き」で解法パターンを高速インストール
毎回電卓を叩いていては、回転させるのに時間がかかりすぎます(労力もかかりますしね)
電車の中や休憩時間などのスキマ時間には、
実際に手を動かさずに頭の中で解法をシミュレーションする「目解き」が非常に効果的です。
【合格者の声】
“電車や仕事の休憩時間に目解きしたこと。最後まで問題を読んで解法を考える習慣がついた
これにより、問題文の情報を正確に読み取る訓練にもなり、ケアレスミスを防ぐ効果もあります。
ただ、目解きだけやっていると「できた気になって」実際解くと全然できない…ということもあり得ます。
定期的に実際に手を動かすことも重要です。
計算と理論を切り離さずに勉強する
「これは計算」「これは理論」と分けて勉強していませんか?
特に財務会計論などでは、計算の背景にある理論を理解することで、計算問題の対応力が格段に上がります。
【合格者の声】
財務会計論。としての勉強にした事で計算と理論を分けなく考えたのが良かった。
なぜこの計算をするのか?という理論的背景を意識することで、
単なる暗記から脱却し、応用問題にも対応できる真の実力が身につきます。
【理論科目】暗記を加速させる反復術
理論科目は、短期間でも劇的に成績を伸ばすことが可能です。
いかに効率よく、そして正確に知識を暗記できるかが勝負。
合格者が実際に実践していた暗記のコツをご紹介します。
理解レベルを「色分け」して可視化する
復習する際に、毎回同じ論点を同じ熱量で読んでいると
まず時間が足りない、そして意外と覚えられていない、という状態になりがちです。
方法はいくつかありますが、
・理解レベルを色分けで可視化する
私が収集した合格体験記では以上のような方法が取られていました。
【合格者の声】
問題集、回転用教材に理解のレベル毎に色分けして付箋の貼り付けやマーカーをすることで、回転の際の重要性の基準にしていました。(赤付箋:全然理解できてない。橙付箋:前回間違えたところ。黄付箋:細かいところ忘れがち)
これにより、「赤(全然ダメ)」と「橙(あと一歩)」の論点を重点的に潰していく、戦略的な復習が可能になります。
「細かい暗記」は直前期に追い込む
これは人にもよるかもしれませんが、
そんなに重要でもないけど知っていれば簡単に得点できるような箇所
については直前期に回してしまう、という手段もあります。
【合格者の声】
企業法の表の内容や監査論の歴史など、細かい暗記は直前までやらない(どうせ忘れるので)(内容に目は通す)
普段は出題実績や重要度の高い論点を重点的につぶす。
その他の論点でも得点がしやすいところは、全く触れないのではなく、直前期にさっと(一応)暗記しておく、というのも有効です。
用語の「定義」を正確に押さえる
なんとなくの理解で用語を使っていると、少しひねられた問題に対応できません。
(そういう問題が特に短答は多いんですよね…)
用語の定義を正確に言えるようにしておくことが、正誤判断の精度を大きく左右します。
【合格者の声】
回転用教材の用語(特に複雑な規定の論点)は何となくの理解で片づけずに、定義をはっきりさせておくことで文章の理解がしやすくなり、知らない文章の正誤判断であったとしても方向性を間違えることは少なくなる。
特に基本的な用語の定義を疎かにしないことが、高得点への近道です。
まとめ:合格の秘訣は「自分に合った方法」を見つけること
今回は、短答式試験合格者のリアルな体験談から「本当にやってよかった勉強法」を厳選してご紹介しました。
たくさんのテクニックをご紹介しましたが、
最も大切なのは、
これらはあくまでも手段の一つで、これらのヒントを参考にしながら「あなた自身に合ったスタイルを見つけること」です。
この記事で紹介した勉強法が、あなたの合格への道を切り拓く一助となれば幸いです。
こちらで短答式合格者が逆に「失敗」した勉強法についても解説しています。
また、全体的な短答式の勉強法についてはこちらでもまとめています。
少しでも皆さんの成績が上がり、早期に合格する一助になれば幸いです。