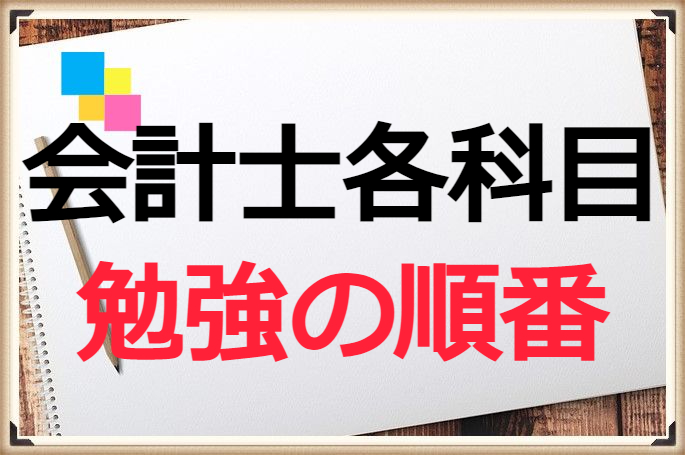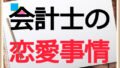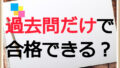・勉強する科目が多くてどれを優先すべきかわからない
・できれば短答式、論文式に分けて教えてほしい

復習する時間の関係から、勉強する順番は結構重要です。
・30代で働きながら公認会計士試験合格
・修了考査合格、公認会計士登録済
・現役会計士としてSNSフォロワー1万人超アカウントで情報発信中
こんにちは!とむやむくんです。
短答式試験であれば4科目、論文式試験であれば6科目。
国家試験の中ではそこまで科目数が多いとは言えませんが、それでも並行して勉強するのには骨が折れます。
一体どの科目から手を付けるべきなのか正解はありませんが、
今回は私が実際にやってよかったな、と思った順番について書いていきます。
予備校は合格実績NO.1のCPAを推奨しています
⇒【割引クーポン】CPA会計学院資料請求
【ストップ!!】監査法人就職のウラ技
簿記を勉強している。前職がある。
実は、これだけで十分就職可能です。
・試験休暇なんと3ヶ月
・年収500万以上
⇒これが『今すぐ』実現できます。
合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。
ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。
情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。
私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。
もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)
各科目勉強の順番(短答式)
まずは短答式試験4科目についてです。
短答式が会計士試験最難関になりますので、勉強の順番は重要です。
まずはここを突破しないことには論文式を受けることはできませんし、
今後の会計士の勉強を進める上で、ここでの勉強の順番は結構重要になってきます。
おすすめの順番
さて私のおススメの順番です。
2.管理会計論
3.企業法
4.監査論
もちろん、予備校のカリキュラム通りに進められるのであれば問題ありません。
ただ、途中から勉強を始めた方はこの順番が私は推奨しています。
この順番の理由
まず、財務会計論が1番最初の理由ですが
単純なことを言えば、この科目だけ点数が2倍だからです。
管理会計論 100点
企業法 100点
監査論 100点
【合計】 500点
短答式試験はこんな内訳になっています。
見てわかる通り、財務会計論を優先すべきとういことがわかりますね。
ただこれ以外にも理由はあって
財務会計論と管理会計論は計算があります。
この計算は授業を受けた後継続的に反復する必要があります。
その関係でできるだけ早い段階で勉強を開始し、できるだけ長く復習・反復をする必要があります。
また、財務会計論や管理会計論の計算は、一回マスターすればある程度試験全体の点数が安定するようになります(理論と違ってそこまで急に忘れるものでもないため)
ただ習得に時間がかかるのが計算ですので、先にやっておくのがいいでしょう(一番勉強していて嫌になるのも計算だと思います)
企業法については暗記量が多い事、
監査論については私も勉強に一番時間をかけなかったため、4番目にしました。
各科目勉強の順番(論文式)
次は論文式試験6科目についてです。
短答式から2科目が追加になり、その科目との配分が大事になります。
今までの4科目だけでも大変だったのに、更にそこに2科目追加…絶望的な気分になったのを覚えています。
ですが、4科目については今までの積み重ねがある分、実際勉強してみると正直短答式の方が大変だったかな?と個人的には感じました。
おすすめの順番
2.企業法
3.経営学
4.財務会計論
5.監査論
6.管理会計論
この順番となります。
こちらもやはり基本的には予備校のカリキュラムに沿って進められるならそちらを優先してください。
独自で進める場合は、色々試しましたが、私はこの順番がベストかと思います。
この順番の理由
論文式から追加される「租税法」「経営学」
この2科目を先にやることは当然です。
特に租税法については習得に時間がかかり、やってない時一番本番でやらかす可能性が高い科目です。
しかし、租税法は努力が反映されやすい科目ですので時間をかけるべきです。
企業法については短答式試験の超暗記型から一変、会計士試験で一番多くの論述を求められる
暗記&現場思考&論述力が求めらえる別科目と化します。
ここを甘く見ていて残念な結果となる受験生は多いです。
しっかり時間をとって、しっかり暗記、対策をするようにしましょう。
財務会計論、管理会計論の計算については短答式の知識をキープしていれば問題ありません。
ただ理論は論述用にインプットを仕直す必要があるので、やはり傾斜配点になっている財務会計は優先度を上げています。
監査論、管理会計論の暗記量は他と比べれば少ないのでこの順位となっています。
(ただ監査論の事例問題は答練等でしっかりなれる必要があります。)
まとめ
雑多ですが各科目の勉強の順番について書きました。
これはすなわち勉強時間、復習の優先度に直結しますので参考になるか思います。
予備校に入学したタイミングが丁度講義開始時期とあっている方、というのは逆に少ないと思います。
ですので、途中からは予備校のカリキュラムに従うとしてもある程度は自分の裁量で勉強を進めなくてはなりません。
効率的に勉強して、高得点を目指しましょう。
【全受験生へ】試験に合格しても、会計士になれるのは4年後です
最短で会計士になるためには
②最短で会計士登録要件を満たす
この2つが必要になります。
①最短で会計士試験に合格するためには
・十分な勉強時間の確保
この2点が何より重要です。
②合格後最短で会計士登録するためには
これが必要です。
まず①「会計士試験合格」について
会計士試験は簡単な試験ではありません。
『解答を暗記しただけの上辺の知識では合格できません』
『勉強時間は社会人は平日5時間、専念生は10時間は必要です』
恐らく大半の方は、思ったように勉強が進んでいないのではないでしょうか。
仕事が忙しくて勉強ができない!
そんな声を何度もお問い合わせで頂いております。
次に②「会計士に必要な実務3年」について
合格後3年たった次の年で公認会計士登録が可能になるので(更に修了考査突破が必要)
合格してから4年は長い!と感じられるかもしれません。
さて、この①会計士試験最短合格②実務要件3年の問題を両方解決する方法があります…
それは、合格前から監査法人へ就職することです。
実はあまり知られていませんが、監査法人には勉強中でも就職できます。
〇受験生の方は簿記知識や会計士の受験経験
これらで監査法人に就職できる可能性が十分にあります。
実際に監査を経験することで
⇒勉強の理解を圧倒的に高めます。
試験休暇中は仕事をしなくていいので
⇒数ヶ月勉強時間を確保ができます。
合格前に実務経験を満たすことで
⇒なんと1年目から修了考査を受験することができます(通常3年)
つまり合格前から監査法人に就職することで、『最短で会計士になることが可能です』
そしてたとえ不合格でも『好待遇で』働き続けることができるのも魅力です。
実は求人情報は一般的には公開されておらず、監査法人のHPにもあまりなく、
『監査法人とつながりの深い転職サイト』を通じて紹介しているのみとなります(どこにでも掲載してしまうと会計や監査に全く無関係の方の応募が殺到してしまうようです)
なので応募するには、『監査法人とつながりの深い転職サイト』へ登録する必要があります。
そうすることでBIG4全ての求人を閲覧・紹介してもらえるようになり、
さらに、登録後は給料交渉や勤務形態(残業無など)の交渉も『全て』やってくれます。
(登録さえすれば求人は見れますので求人を『見るだけ』というのももちろん可能です)
その中でも私はBIG4の求人を多く掲載し、業界トップクラスの実績があるということで、こちらのサイトを使っていました↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)
ちなみに、早めに登録しておくとこんなメリットがあります。
・必要なスキルが明確になり勉強の指針になる
・合格後の定期採用と並行して行動することができる
登録や利用自体に時間はかかりませんから、勉強の合間の数分で可能です。
このブログを読んでいらっしゃる方は、そもそも予備校や周りの意見だけでなく、ご自分で動こうという強い意志を持っている方です、私は予備校の言いなりでしたから、本当に尊敬します。
残業が多くて勉強する時間が作れない、収入も増やしたい!
少しでも早く合格して、早く公認会計士になりたい!
その願望は『行動』を起こせば叶えることができます。
そのためにはまず、選択肢を増やさなくてはなりません。
利用は完全無料、是非登録して見て下さい。
勉強法関係の他記事もチェック!
勉強法関係の記事をこちらにまとめています。
その他予備校、監査法人、会計士の魅力についてはこちら
(↓画像をクリックで飛べます↓)