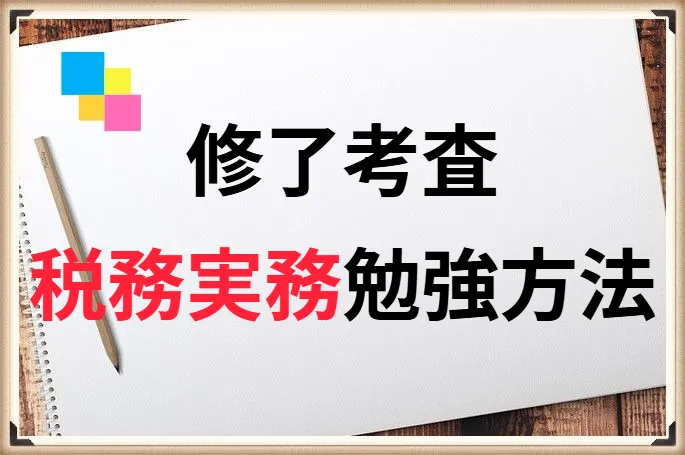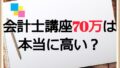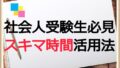この記事は以下のような方におススメです。
・税務実務の具体的な勉強方法が知りたい方

こんにちは!とむやむくんです。
修了考査と言えばご存じの通り、公認会計士登録するための最後の砦、最後の試験。
その中で最も対策に時間がかかる科目ともいえるのが、税に関する理論及び実務、いわゆる「税務実務」です。
公認会計士試験時代には触れていない税科目も多く登場し、しかも範囲も広くなっている、
本当にやっかいな科目です。
①計算の範囲を全て網羅することはできない
②理論は特別の対策不要
③過去問、答練箇所を中心にした対策が最重要
これから紹介する勉強方法は私が実際に試してこれは効果があったな、と思うものをまとめたものです。
本番は何とも言えませんでしたが、税務実務に関しては『答練ではほぼトップの成績』を取っていましたので、
ある程度参考になる情報が提供できると思います。
あくまでも一つの勉強法として参考になれば幸いです。
(一応今回は修了考査まである程度時間がある方向けに書いています)
☆この記事の信頼性について
筆者は実際に修了考査を受験、一発合格しており、合格者として税務実務の勉強法を発信しています。
今の法人から一刻も早く『脱出』したい方へ
BIG4の雰囲気にもううんざり…
膨大なタスク・残業がキツイ…
監査なんてそもそも好きじゃない…
→何も今の職場に執着する必要は"全く"ありません
・未経験から他業種への好待遇転職
・もはや完全に残業しない、週3勤務
⇒こんなのは『簡単に』達成可能です。
ご存じかとは思いますが、転職市場での会計士(合格者)の評価は半端じゃないです
ただ、会計士の価値をよくわかっている専門のエージェントでないと、大失敗することがあります。
私は業界に精通しており、業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。
もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓
税務実務の勉強方法:基本方針
修了考査の税務実務における出題範囲をご存じでしょうか?
修了考査の受験案内には以下の通り記載されています。
公認会計士が行う業務で必要とされる税に関する専門的応用能力を修得しているかどうかの確認を行うことを目的とし、我が国における税に関する理論及び実務全般について出題します。
〇出題に関する基準・出題項目等〇
・法人税に関する理論及び実務
・所得税に関する理論及び実務
・消費税に関する理論及び実務
・相続税・贈与税に関する理論及び実務
・地方税に関する理論及び実務
・その他上記に関連する租税法及び国税通則法に関する理論及び実務 等
日本公認会計士協会「修了考査について」より抜粋
まあ、つまり
法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税、地方税の計算と理論全部範囲。
ということです。
公認会計士試験時代に触れているのは法人税・所得税・消費税だと思いますので、
範囲が広がっていることが分かると思います。
(しかも法人所得消費に関しても範囲普通に出題範囲広がってます)
まあ普通に考えて、全ての範囲を網羅することはできません。
まして大半の方は働きながらの受験になるわけですから、時間は有限。
まず全ての範囲を徹底的に対策することはコストパフォーマンスが悪すぎる、ということは念頭に置いておきましょう。
税務実務の勉強法:計算理論共通
さて、全ての範囲を徹底的に潰すのが難しいのはご理解いただいたと思いますので、
具体的な勉強法について紹介していきます。
まずは計算・理論に共通する勉強方法として
・答練対策
・テキスト対策
・予備校の利用
それぞれについて解説していきます。
(なお、他科目とも重複する箇所が多いことはご了承ください)
理論対策について
いきなり脱線してしまいますが、
税務実務における理論対策について触れておきたいと思います。
予備校の講師の方にも言われたのですが
税務実務において理論対策を特別に行う必要はありません。
というか現実的に時間が足りなすぎます。
計算の手法を覚えて、それを本番どれだけ書き出せるか勝負です。
なので計算を一生懸命勉強すればそれで十分です。
私も答練の理論に関しては抑えましたが、理論だけの特別のが対策はしていません。
過去問対策
修了考査のどの科目にも言えることですが、
過去問対策と答練対策は必ず必要です。
会計士試験と違い、入念な試験対策に割く時間がない中、
大半の方が対策してくるのがやはり過去問と答練だからです。
そんな過去問対策ですが、私の場合は
早速で申し訳ないのですが…
やってません。
具体的に言えば、解いてはいません。
見ただけです。
1回だけ。
どんな問題が出ているのかな、難易度はどれ位なのかな、を確認した程度です。
理由としては、会計実務とほぼ同じですが、
・回によって難易度や出題傾向が全然違うこと
・改正されている論点もあるということ
受験生の中には過去問を反復している方もいたようですが、私はしませんでした。
それよりも、次に書く答練の反復をものすごくやりました。
答練対策
答練に関してですが
私は答練対策がかなり肝になってくるかな、と思う所がありましたらから
1年前の答練も入手し、対策を行っていました。
TAC、CPA両方とも入手していたのですが、税務実務の答練はひたすら重い!(本なのかな?位の厚さがあります)
そのため、CPAの方は触れず、TACの方のみ自分の受験年と1年前の答練を反復しました。
(具体的に言えば受験できなかった年の分もあったので、合計3年分答練を回すことに…大変でした)
さて、『理論』については先ほど触れたように
答練箇所だけは反復して学習しました。
答練箇所に関しては一応解説もきちんと読んで理解するようにしていました。
『計算』についてですが、
会計実務と違いこれはひたすら解き直しました。
(会計実務は解き直してないです)
時間がかかってしょうがない。
でも解法をマスターするには解き直しが一番です。
可能な限り電卓も打って、眺めるだけでなく実際手を動かしました。
テキスト対策
税務実務に関しては、
答練出題箇所や過去問出題箇所をテキストに転記することをしていません。
TACの講座ではとんでもなくわかりやすくテキスト作りをしてくれましたので、
一見して重要な箇所、覚える箇所がわかるようになっていました。
税務実務ではテキストも積極的に読み込むようにしていました。
例題も講義で触れた個所や自分が苦手だなと感じる箇所は積極的に解きました。
予備校の利用
予備校については私は利用すべきだと考えています。
大半の方が利用していますし、何と言ってもやはり費用対効果は高いと思います。
補習所のテキストから対策…となると、やはりかなり厳しかったです(私は)
監査法人勤務の方の多くは、予備校代も補填してくれる場合があるでしょうから、通わない手はありません。
(どこかで記事も書こうかとは思っていますが、体感ではCPAとTACが多く、CPAが一番多い印象です。)
さて、税務実務における予備校の利用についてですが(私はTACでした)
最高の一言です。
先程も触れたようなテキストの作り込みもそうですが、
講義も分かりやすく、答練もしっかりしていて、何も文句ありません。
積極的にテキスト作りをしてくれますが、それ以上に講師の方の分かりやすい説明も書きこむようにしていました。
出来上がったテキストを見ると、なんてわかりやすい。
もし税務だけでどこか予備校ないですかと言われたら間違いなくTACをおすすめします。
(私の時は三田先生という方でした、ありがとうございました)
税務実務の勉強法
理論に関しては特別な対策は不要(答練のみ反復)ということは書きましたので、
税務実務計算の時期別の勉強法について触れていきます。
初期
答練開始前から、前年度の答練を解き直していました。
ぜっっっんぜんできませんでした。
1回目、全て解き、
2回目、できなかったところはチェック(書き込み)
3回目、チェック箇所を反復
4回目、チェック箇所を反復
5回目、チェック箇所を反復
6回目、全て解き直し再度チェック(書き込み)
7回目、チェック箇所を反復
・
・
・
いや何周したんだよと。
(定期的に全て解き直していました)
さすがに答練開始前までには3周位?しかしていないと思いますが、
本試験まで含めたら相当回したと思います。
初期は1日1回分、TACは答練が4回ありますから、4日で4日分回していました。
ただ当年度の答練が終わると全部で8回分ありますから
(なんなら私は12回分ありましたから)
昔の答練は1日で2回分回したりして、なんとか1週間で全ての範囲回せるようにしていました。
ちなみにこれと並行してテキストの読み込みも徐々に進めていました。
テキストに関しては2週間で1周できるくらいで読み込みをしていました。
直前期
税務実務に関しては特段初期と勉強方法は変わりませんでした。
1週間で全答練、テキストの範囲を回せるようにしてひたすら回しました。
きっとみなさんが思っている事
恐らくみなさんは、
いや、時間かけ過ぎでは?
と思われたかもしれません。
確かにその通りだと思います。
私はたぶん全受験生の中でもトップレベルで税務実務に勉強時間をかけたと思っています。
ですがそれだけ税務実務は重要な科目だと思っていましたし、得意科目にもできました。
むしろ税が好きになりましたし、実務にも積極的に触れたくなりました。
必要最低限でいい、ということであれば
当年度の答練の反復、該当箇所のテキストの読み込み、が最もコスパは良いと思います。
ですが、得意科目にしたい、せっかくなら勉強内容が実務に役に立ったらいい、ということであれば
積極的に勉強する価値が税務実務にはあると私は思います。
おまけ:各税科目の印象
税務実務に関しては複数の税科目が混在しており、
各税科目勉強の印象が全く違います(かける時間も)
なので各税科目について印象や重要度などを書いていこうと思います。
法人税
印象:重い、でも点数は取りやすい
ぜったい一番大事、やればやるほど点数が伸びる税科目です。
ただその分範囲も広いです。
(TACは税務実務7冊のテキスト中3冊が法人税です)
別表5とは最後までお友達になれませんでした。
消費税
印象:範囲は広くない、ただ落とせない
消費税は超重要税科目の一つですが、範囲はそこまで広くありません。
テキストも薄いですし、対策は取りやすいと思います。
ただ、
解けばわかるかと思いますが、
途中の回答を間違うと後の問題がつられて全て不正解になるという…
かなり慎重に解く必要がある税科目です。
相続税・贈与税
印象:会計士試験でない範囲、割となじみやすい
相続贈与は会計士試験でまったく未出題の範囲。
初めて触れることになる科目かとは思いますが、
実際の生活で役に立つちしきではありますから、とっつきやすいとは思います。
出題される箇所もある程度きまっており、しっかり対策すれば点数はとれるイメージです。
所得税
印象:あまり出ない印象
年によってはごそっとでるイメージはありますが、
予備校の講師の方も言うようにあまり重要視しなくても大丈夫な税科目です。
(会計士試験ではめちゃくちゃ出ましたよね)
出やすい所得(譲渡所得とか)を積極的に抑える形で良いと思います。
地方税・国際課税・財産評価など
印象:時間がないと切る人もいる?
地方税関しては法人税と絡めたりしてでることもありますが
国際課税や財産評価などは対策自体あまりしない人もいる印象です。
私は重要と言われた箇所はやりましたが、確かに積極的に勉強した範囲ではありません。
さいごに
税務実務は勉強がかなり大変かとは思います。
そして本試験で点数が取れるかも、出題形式が大きく変わったりすると何とも言えません。
ですが実際の生活で役に立つ知識ではありますし、実務に結びつく実践的な科目だと思います。
私の年の税務実務の本試験の感想としては、簡単に見えて意外と取れない、でした。
会計士登録まであと少しです!
最後の勉強、がんばりましょう!